こんにちは。内科系病棟で看護師をしているめめです。
今回は、高齢者に多く、見落としがちな誤嚥性肺炎について、病態と病棟での実際のケアを交えてお話しします。
🔍 誤嚥性肺炎とは?
誤嚥性肺炎は、「唾液や食べ物、胃内容物などが誤って気道に入ってしまうことで起こる肺炎」です。
特に高齢者では、嚥下機能の低下や、認知症・脳血管障害による意識の低下があるため、発症リスクが高くなります。
✨ ポイントは「気づきにくさ」
普通の肺炎と違って、はっきりとした発熱や強い咳が出ないことが多いのが特徴です。
そのため、ちょっとした「変化」に気づくことが大切になります。
🏥 病棟でよく見る誤嚥性肺炎の兆候
私たちが病棟で「これは誤嚥性肺炎かも?」と感じる場面はこんな時です:
- 食後に「むせ」が増えた
- 会話中にゴホゴホと空咳をしている
- 食欲が低下している
- 発熱はないけど、SPO₂が下がっている
- いつもよりボーッとしている(意識レベルの変化)
レントゲンで右肺下葉に影が出て、誤嚥性肺炎と診断されることがよくあります。
👩⚕️ 看護ケアのポイント
- 食事中の観察強化:嚥下の様子や咳・むせの有無をしっかり記録
- 食事姿勢の工夫:できるだけ座位で、顎を引いてもらう
- 口腔ケアの徹底:細菌を減らすため、毎食後のケアが大切
- 吸引や体位ドレナージで痰を排出しやすくする
- 医師へ報告するときは、「発熱・呼吸状態・SPO₂・痰の性状・食事摂取状況」をセットで報告する
※次に病棟でよく見かける誤嚥性肺炎の典型的な患者さんの例を紹介します(※個人情報に配慮し、実在の人物ではなく、臨床でよくあるパターンをモデル化しています)。
🧓【患者例】90歳・男性 Aさん
診断名:誤嚥性肺炎
🔹背景・既往歴
- 年齢:90歳
- 独居 → 転倒により骨折し、入院中にADL低下
- 既往歴:脳梗塞(軽度の構音障害・嚥下機能低下あり)、高血圧、認知症(中等度)
- 常に車椅子移動、食事はミキサー食+トロミ水
🔹入院経過と変化
- 入院後2週間目
- ある日、微熱(37.4℃)とSPO₂低下(92%)
- 日中に咳き込むことが増えた
- 食事中にむせる回数が増加、食欲も低下
- 痰が増え、**喉がゴロゴロしている音(湿性ラ音)**が聴取される
- 胸部レントゲンで右肺底部に浸潤影 → 誤嚥性肺炎と診断
🔹看護ケア内容
- 経口摂取を一時中止し、点滴で栄養管理
- 酸素投与開始(1L/分)
- 看護師による吸引・口腔ケアの強化
- 食事再開に向けて、ST(言語聴覚士)による嚥下評価を依頼
- 体位管理(半座位の維持)、肺炎の悪化防止に向けた排痰介助
🔹その後の経過
- 抗生剤治療により熱は2日で解熱
- 呼吸状態も安定し、再び食事再開(ゼリー・トロミ付き水から)
- STと連携しながら、安全な食形態に移行中
- 今後は在宅復帰に向けてリハビリと多職種連携が課題
このように、誤嚥性肺炎は「なんとなく元気がない」「微熱」など小さなサインから始まることが多く、早期発見がカギになります。
🌱 最後に
誤嚥性肺炎は、再発も多く、患者さんやご家族にとって大きな負担になる病気です。
でも、ちょっとした変化に気づいて早く対処できれば、悪化を防ぐことができます。
病態の理解と観察力を磨いて、これからも一人ひとりの患者さんに寄り添っていきたいです。
次回は誤嚥性肺炎についての「観察ポイントまとめ」や「ST・栄養士との連携方法」などを深掘りする記事について書く予定です。
他にも取り上げてほしい病態があれば、コメントやメッセージで教えてくださいね📝

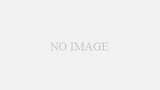
コメント