こんにちは。リハビリ病棟で勤務している看護師めめです。
今回は「脳梗塞後の患者さんへのリハビリと看護の関わり」について、症例を交えながらお話しします。
🧠 脳梗塞とは?
脳梗塞は、脳の血管が詰まり、血流が止まることで神経細胞がダメージを受ける病気です。
発症後は、麻痺・嚥下障害・認知機能の低下・失語など、さまざまな後遺症が残る可能性があり、早期のリハビリ・ケアが生活再建の鍵になります。
🧓【症例】右中大脳動脈閉塞による左片麻痺の70代男性Dさん
🔹背景・既往歴
- 高血圧・高脂血症あり
- 独居で元は自立生活
- 発症後、緊急入院→t-PA実施→急性期治療終了後に回復期リハ病棟へ転棟
🔹現在の状態
- 左上下肢麻痺あり、歩行困難
- 嚥下機能軽度低下(ミキサー食)
- 短期記憶障害と軽度の失語症
- ADL:全介助 → 徐々に一部介助へ移行中
🔍 看護師が意識したい観察ポイント
① 麻痺側の状態・活動の変化
- 関節拘縮、筋緊張の左右差
- 自己抜去・転倒のリスク
- 自分の身体への無関心(半側空間無視)
② 認知・情動の変化
- 感情の起伏が激しくなる(感情失禁)
- 指示理解や記憶力の低下
- 「やる気がない」と見えがちな無関心(アパシー)
③ 嚥下・食事状況
- 食事中のむせ・咳嗽
- 食形態への拒否・疲労の様子
- 食事中の集中力の低下
④ 排泄・更衣・清潔
- トイレまでの移動方法・手順理解
- 下着の上げ下げ動作ができるか
- 皮膚トラブルや失禁への対応(褥瘡予防)
🤝 多職種連携での関わり方
👩⚕️ PT(理学療法士)
- 起き上がり、立位、歩行の訓練
- 看護師がベッド上での動作方法を統一して介助
- 移乗・ポジショニング方法を相談して転倒予防
🧑🦲 OT(作業療法士)
- 食事動作、更衣動作、トイレ動作などADL向上支援
- 環境設定の工夫(手すりの設置、物の位置など)
- 自助具の使用方法の確認・共有
👄 ST(言語聴覚士)
- 嚥下評価(VFやVE)・言語機能の訓練
- 食事時の姿勢や介助の工夫
- コミュニケーション支援(意思表出手段の確保)
🧠 医師・ソーシャルワーカー
- 退院支援に向けた情報共有(家族構成・居住環境)
- 支援制度・介護保険の導入調整
👩⚕️ 看護師としての関わりのコツ
💬 その人の「できること」に着目
- 「まだできない」ではなく「これならできる」を見つける
- 成功体験を日々のケアで積み上げていく声かけが大切
⏳ 焦らず、でもタイミングは逃さない
- 日々のバイタルや疲労感を見て、リハのタイミング調整
- 朝の清潔ケアや排泄動作は“自然なリハビリの場”
✍️ 情報共有をこまめに
- OT・PT・STとの記録や口頭での連携で“抜け”を防ぐ
- 看護師からの気づきが、訓練内容のヒントになることも
🔚 まとめ
脳梗塞後のリハビリは、多職種連携×日常ケアの積み重ねがとても大切。
患者さんの「できる」を見つけ、「またできた!」と実感できる日々を支えるのが、看護の力です。
ご希望の内容があれば、ぜひコメントで教えてください😊

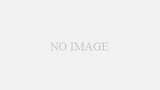
コメント