こんにちは。内科病棟で働く看護師のめめです。
今回は、心不全について、病態の基本から、現場での観察・ケア、そして多職種との連携までをまとめてみました。
💔 そもそも心不全とは?
心不全は、「心臓が全身に十分な血液を送り出せなくなった状態」。
つまり、心臓のポンプ機能が落ちて、体に水分が溜まったり、臓器がうまく働かなくなったりする状態です。
原因は高血圧、心筋梗塞、不整脈、心筋症などさまざま。高齢者に多く、再入院率も高い疾患です。
🧓 【症例】心不全で再入院された80代女性Bさん
🔹背景・既往歴
- 80代・女性/心不全で2回目の入院
- 高血圧・慢性腎不全・軽度の認知症あり
- ADL:自立~一部介助
- 1週間前から「息切れ」「食欲低下」「体重増加」
🔹入院時の状態
- 呼吸苦あり、SPO₂ 92%(室内気)
- 浮腫(下腿に指跡が残る)
- 頻尿・夜間のトイレが増えた
- 聴診でラ音(湿性雑音)あり
- レントゲンで肺うっ血/BNP高値
→ うっ血性心不全と診断
🔍 看護師が観察すべきポイント
① 呼吸状態
- 呼吸数・SPO₂
- 労作時呼吸困難(トイレ歩行後に息切れする など)
- 寝る姿勢(仰臥位を嫌がり、起座呼吸になっているなど)
② 浮腫・体重変化
- 下肢・仙骨部の浮腫(毎日視診・触診)
- 体重の急増(前日比+1kg以上なら要注意)
③ 尿量・利尿効果
- 利尿薬投与後の尿量チェック(時間・量・色)
- トイレの回数と様子(夜間頻尿が増えているか)
④ バイタルサイン
- 血圧の変動
- 脈拍のリズム(不整脈が出ていないか)
⑤ 食欲・意識
- 食欲不振は「うっ血の悪化」のサインかも
- 会話中の眠気、集中力低下
🤝 チームでの連携ポイント
🫀 医師との連携
- 観察所見(体重・浮腫・呼吸苦・尿量)を正確に報告
- 利尿薬調整のタイミングで情報共有
🧑⚕️ 栄養士との連携
- 食事摂取量が減っている → 栄養補助の提案
- 塩分制限(6g未満など)の理解と継続ができているか確認
👟 リハビリスタッフとの連携
- 呼吸苦による活動量の低下 → 廃用予防に向けた歩行訓練
- 転倒リスクのアセスメント(浮腫・ふらつき)
💡 まとめ
心不全の患者さんは、わずかな変化を早く見抜くことが予後を左右します。
看護師としての「観察力」に加えて、医師・栄養士・リハビリ・薬剤師など多職種との情報共有が早期対応のカギになります。
患者さんのQOLを守るためにも、日々の小さな変化に敏感でありたいですね😊

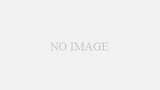
コメント